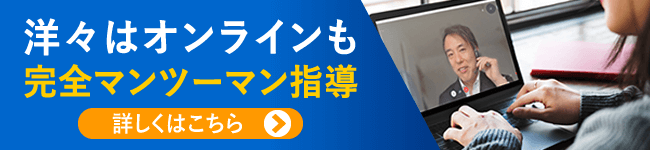一般と総合型選抜の準備を両立し、基礎学力をしっかり固めて憧れの慶應義塾大学法学部にFIT入試で合格!
「一般入試と総合型選抜入試の準備を同時に進めるのは悩みも多かったですが、両方に挑戦することを前向きに考えられました。」
R.Hさん
立教女学院高校
慶應義塾大学法学部FIT入試A方式・B方式 合格

合格おめでとうございます!合格した今の気持ちを教えてください。
合格の知らせをスマートフォンで見たとき、最初は全く実感がなくて驚きました。結果が出てから数日間はまだ信じられず、気づけば一般入試の勉強を続けていました。周りの人に「おめでとう」と言われて初めて、少しずつ実感が湧いてきた気がします。一般入試のための模試などもあったので、しばらくは「合格した」という実感を忘れてしまっていたほどです。
慶應義塾大学法学部を志望したきっかけを教えてください。
人種問題を解決したいという思いがずっとあり、中高時代にはそのテーマで学生団体を立ち上げました。より深く人権について学びたいと感じたことが、法学部を志した一番の理由です。また、立教大学の附属校に通っていたこともあり、「内部進学ではなく高みを目指してみたい」という気持ちを抱いていました。慶應への挑戦は、高校3年の4月ごろにはすでに決めていました。
なぜFIT入試で受験しようと考えたのですか?
FIT入試はA方式とB方式の両方を受験しました。もともとは一般入試を目指していましたが、両親が総合型選抜入試を紹介してくれたことがきっかけで、挑戦することを決めました。一般入試と総合型選抜入試の準備を同時に進めるのは悩みも多かったですが、もともとマルチタスクが得意な方だったので、両方に挑戦することを前向きに考えられました。今しかできない経験を積める機会が貴重だと思えましたし、何より総合型選抜に向けた勉強も自分には楽しく感じられたので、最後まで続けることができたのだと思います。
出願書類はいつ頃からどのように準備しましたか?
書類の準備は高校3年の4月ごろから始めました。最初のうちは洋々でメンターやプロと議論しながらしっかりと基礎を固め、ある程度書類の形ができてからは、洋々以外の様々な方にも見てもらってブラッシュアップしていきました。書類の準備を始めた時期としてはちょうど良く、早すぎず遅すぎずのタイミングで集中して進められたと思います。
本番当日はいかがでしたか?
A方式を受験した翌日にB方式を受けたので、会場までの道や雰囲気には慣れていて、少し安心感がありました。ただ、B方式の方が受験者数が多く、「例年の二次の倍率よりも高そうだな」と思い少し不安になりました。B方式の総合考査は、図表問題は比較的読み取りやすく、英語の長文もこれまでにない形式ではありましたが、一般入試に向けて行ってきた学習を生かせたことで、論点を大きくずらすことなく書けたと思います。
一番緊張したのは面接前の控室でしたが、実際の面接官は思っていたよりも優しく、志望理由書に書いた内容を中心に深く質問してくれました。自分の熱意を丁寧に伝えられたと思います。面接終了後は自分の最大限を出し切ることができたな、と手ごたえを感じました。
入学後の抱負を教えてください。
法学部からの合格を頂くことができたので、法律について深く学びたいです。特に、自分が関心を持ち続けてきた人種問題の解決に関わるような分野を重点的に学びたいと思っています。勉強以外では、これまで続けてきたダンスをサークルなどで引き続き楽しめたら嬉しいです。
全体を振り返って、その他に洋々の良かった点があれば教えてください。
洋々の良かったところは、皆さんとの距離がとても近く、どの講師やメンターも親身に関わってくれたことです。今まで通ってきた塾とは全く違い、「教わる場所」というよりも「一緒に考え、発想を広げる場所」という感覚でした。時には鋭い質問をされることもありましたが、そうした対話の積み重ねがあったからこそ、自分の考えに対する解像度が上がっていったと思います。
また、校舎の立地が良く、日常的に通いやすかったことも助かりました。
今後受験する方へのアドバイスをお願いします。
まず、基礎学力をしっかりつけておくことが何より大切だと思います。最近は総合型選抜の受験者が増えていますが、単に「一般より入りやすい」ではなく、「自分が学びたいことと大学の方向性が合っているか」を考えることが重要です。大学に入ってからも学び続けられるだけの学力が必要ですし、ビジョンを実現するためにも土台が欠かせません。
総合型選抜と一般の準備は内容が重ならない部分もありますが、両立しておく方がメンタル的にも安定します。また、一般受験用の模試を継続的に受験していたことや、師事したい教授の論文を読み込んだことで、小論文を書く文章力が向上したと思います。小論文は知識をインプットするだけでなく、それをアウトプットする文章力を鍛えることも必要だと感じました。そのため、自分が書ける文章よりも一段階レベルの高い文章を読み、そこで得た語彙などを実際に使うことを心がけました。これらを反復することで、自分が伝えたい内容を正確かつ簡潔に伝えられる文章が書けるようになったと感じています。
ありがとうございました。R.Hさんの今後のご活躍を、洋々一同心よりお祈り申し上げます。